味噌汁は日本人の食卓に欠かせない存在ですが、一人暮らしでは「分量がわからない」「鍋を使うのが面倒」「一杯だけ作るのは効率が悪い」といった悩みも多いものです。
特に初めて自炊に挑戦する人にとっては、味噌の量や水加減、だしの取り方など小さな疑問が積み重なり、作るのをためらってしまうこともあるでしょう。
本記事では、そのような不安を解消するために、一人分に特化した味噌汁の作り方を徹底解説します。
結論からいえば、一人分の味噌汁は水200mlに味噌大さじ1弱、だしの素小さじ1/2が目安です。さらに、好みに応じて具材や味噌の種類を変えるコツ、失敗しない加熱の順番、洗い物を減らす工夫なども詳しく紹介します。
その上で鍋を使わずにレンジやポットでも手軽に作れる方法を提案し、忙しい朝や夜食でも短時間で作れる実践的な手順をまとめました。
記事のポイント
- 一人分の基本分量(水200ml・味噌大さじ1弱・だしの素小さじ1/2)を押さえる
- 鍋を使わないレンジ・電気ポット調理も可能
- 具材や味噌の種類でバリエーションを楽しめる
- 保存や減塩の工夫で毎日続けやすくなる
味噌汁の作り方一人分基本手順と分量
管理人が「味噌汁=幸せ」という事実に気づいた瞬間

それは、管理人が以前1か月ほどフィリピンに旅に行っていたときのこと。
自分は海外に行ったら現地のローカル料理以外食べたくない派なので、毎日毎日味の濃いフィリピーノスタイルの食事が続いてました。
そして旅の終わりに日系のダイビングショップでダイビングをしたときに出てきたのが、和食のお弁当プラス「味噌汁」。
そして久々に味噌汁を口にした瞬間に感じたのは衝撃的な旨さ。
体中から湧き上がる幸福感にアイアムジャパニーズと叫びたい気持ちになったのでした。
その時にこんなに旨いものを日常的に口にしていたことの幸福に初めて気づき、以来幸せとは毎日味噌汁が食べられることと定義しています。
そんな管理人が、美味しさとコスパと作る手間のバランスを考えてたどり着いた現状の一人暮らし味噌汁レシピは以下の通り。
- 水150㏄に冷凍あさり20gと冷凍野菜(管理人は小松菜推し)を投入し沸騰させる
- 即席みそ汁の入ったお椀にそれらを投入して完成
1杯約60円で手に入る幸せをお試しあれ。
一人分の標準量何mlかお椀サイズ早見表

一人分の味噌汁を考えるとき、最初に知っておきたいのは「水の量」です。
一般的にお椀1杯は180〜200ml程度が目安となっており、家庭でよく使う標準的なサイズであれば200ml弱を想定すれば失敗しにくいでしょう。
大きめのお椀を使う場合は220mlほど必要になることもありますし、小さめのお椀なら150ml前後で十分です。
分量が多すぎると味が薄まり、少なすぎると具材のバランスが崩れるため、基本は200ml前後を基準に考えると良いでしょう。
また、この水量は味噌やだしの濃さを決める基準にもなり、味の安定に直結します。
さらに普段使うお椀のサイズを把握しておけば、計量カップを使わなくても感覚的に水の量を調整できるようになります。
| お椀のサイズ | 水の目安量 |
|---|---|
| 小さめ(直径9cm程度) | 150〜170ml |
| 標準(直径10cm程度) | 180〜200ml |
| 大きめ(直径11cm以上) | 210〜230ml |
この目安を把握しておくと、毎回の味噌汁作りが安定しますし、自分の好みに合わせて微調整することも可能になります。
例えば具だくさんにしたい日は少し多めに、濃いめが好きな人は少なめにするなど、応用の幅が広がります。
味噌の量は何グラム?大さじ小さじでは?

味噌の分量は水200mlに対して大さじ1弱(約15g)が標準です。
ただし味噌の種類や塩分濃度によって適量は変わります。
減塩味噌なら大さじ1強、辛口の赤味噌なら大さじ2/3程度でも十分とされます。
合わせ味噌を使うときは標準の15g前後を目安にしつつ、具材やだしの種類に応じて微調整するとバランスが取りやすいです。
計量スプーンがない場合の目安は「親指の先ほどの量=約5g」と覚えておくと便利で、手軽に量を見極められます。
さらにティースプーンや箸先でおおよそを量る方法を知っておくと、外出先や旅行中でも応用可能です。
味噌は水分量や具材の吸い込み具合によっても仕上がりが変わるため、同じ分量でも若干の調整が必要になることを理解しておくと安心です。
| 水の量 | 味噌の量 | 計量スプーン換算 |
|---|---|---|
| 150ml | 約10g | 小さじ2 |
| 200ml | 約15g | 大さじ1弱 |
| 250ml | 約18g | 大さじ1強 |
また、実際には味噌の種類ごとの特徴も影響します。
米味噌は比較的標準的な使いやすさがありますが、豆味噌は濃厚で少なめの量でしっかりとした味わいになります。
白味噌は甘めでやや多めにしてもバランスが取りやすいのが特徴です。この違いを知っておくと、自分の味噌汁をより自在にコントロールできるようになります。
味噌は直接鍋に入れるのではなく、おたまにとってだし汁で溶き伸ばしてから加えるのが基本です。こうすることでダマにならず風味も保てますし、味の均一性も向上します。
さらに一度に溶かしきらず数回に分けて加えると、仕上がりの味が安定しやすくなります。
だしの素・顆粒だし・白だしの分量

だしの取り方が難しいと感じる一人暮らしには、顆粒だしや白だしが便利です。
目安は顆粒だし小さじ1/2(約2g)を水200mlに対して使用。
白だしの場合は大さじ1程度がちょうど良いでしょう。顆粒だしは保存が利くため一人暮らしにはとても扱いやすく、袋入りやスティック状で販売されているタイプを常備しておくと安心です。
白だしはうすめるだけで使えるので手間がかからず、麺類や煮物などにも応用できる万能調味料でもあります。
状況に合わせてうまく使い分けると、味噌汁の味に幅を持たせられます。
| 水の量 | 顆粒だし | 白だし |
|---|---|---|
| 150ml | 小さじ1/3 | 小さじ2 |
| 200ml | 小さじ1/2 | 大さじ1 |
| 250ml | 小さじ2/3 | 大さじ1強 |
顆粒だしを使う場合は、味噌を加える前に完全に溶かしておくと失敗しません。
しっかり溶かすことで味が均一になり、雑味も減ります。
白だしは塩分も含まれるため、味噌の量をやや控えめにするのがコツです。
また白だしの種類によっては甘みや旨味の強さが異なるため、まずは控えめに入れて後から味を見て足すのが失敗を防ぐポイントです。
さらに、だしの種類を変えるだけで仕上がりの印象が大きく変わるため、料理に合わせて顆粒だしと白だしを使い分けると一人暮らしでも飽きずに楽しめます。
基本の作り方~手順・火加減・味噌の溶き方

基本の一人分味噌汁の流れは次の通りです。
- 小鍋に水200mlとだしの素を入れて中火にかけ、軽く沸騰する直前まで温める
- 沸騰前に具材(豆腐やわかめ、ねぎ、乾燥野菜など)を加える。火の通りにくい根菜類はあらかじめ薄切りや下ゆでをしておくと時短になる
- 具材に火が通ったら火を止める。ここでぐらぐら煮立たせないのがコツ
- 味噌をおたまにとり、鍋のだし汁をすくって少しずつ溶き伸ばす。数回に分けて行うと均一に溶けやすい
- 味噌が完全に溶けたら再び弱火にして温度を調整し、お椀に注ぐ。必要であれば最後に青ねぎや七味を散らす
ポイントは「味噌は必ず火を止めてから加える」こと。
沸騰させると香りや風味が飛んでしまうため注意が必要です。
また、火加減は強すぎるとだしが濁り、弱すぎると具材に火が通りにくいので、基本は中火→弱火でコントロールするのがベストです。
調理に慣れてきたら、好みのタイミングで具材を入れる順番を変えたり、溶き卵を加えるなどアレンジも楽しめます。
計量スプーンなしで量る目安とコツ

計量スプーンがなくても、味噌やだしの量は身近なもので目安がつけられます。実際に自炊に慣れている人は「手の感覚」で調整することも多く、ちょっとした工夫で十分代用が可能です。
家庭に必ずあるコップやマグカップ、指先の大きさなどを基準にすれば、外出先や旅行先でも役立ちます。以下は便利な目安例です。
- 味噌:親指の先=約5g、ゴルフボール大=約20g、ティースプーン山盛り=約7g
- 顆粒だし:小袋タイプ1/2=約2g、ひとつまみ=約1g
- 水:マグカップの8分目=約200ml、ペットボトルキャップ1杯=約7ml(約30回分で200ml)
さらに工夫として、普段から自分のよく使う器やカップの容量を把握しておくと失敗が減ります。
慣れてくると「見た目の感覚」で調整できるようになり、忙しい朝や夜の調理時間を大幅に短縮できます。
また、繰り返すうちに「今日は濃いめがいい」「薄味にしたい」といった好みに応じた微調整も自然にできるようになり、毎日の味噌汁作りがより自由で楽しくなります。
忙しい朝は、この「目安化」が特に役立ち、わざわざスプーンを探さなくても安定した味を作れるようになります。
味噌汁の作り方一人分のアレンジと工夫
鍋なし電子レンジでの一人分レシピ
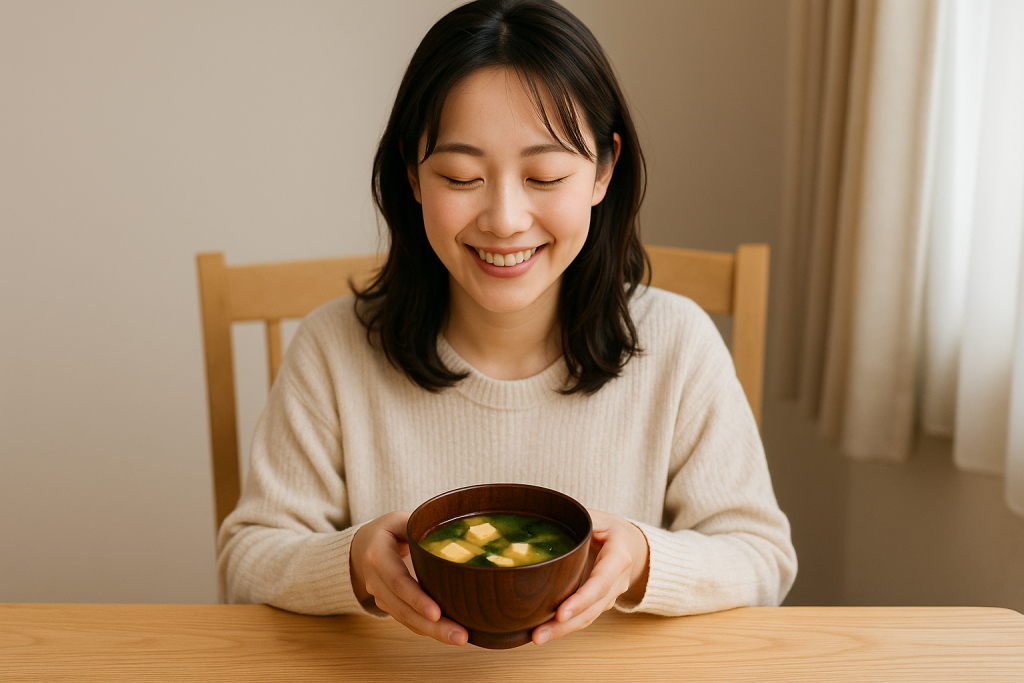
鍋を使わずに作れるのが電子レンジ調理。耐熱マグカップに水200mlと顆粒だし、具材を入れ、ラップをして600Wで2分加熱。
その後、味噌を溶き入れて30秒追加加熱すれば完成です。洗い物が少なく、忙しい朝や夜食にもぴったりです。
さらに工夫すると、電子レンジでも具材の火の通りを均一にできます。
例えば豆腐はあらかじめ小さめに切っておくと中まで温まりやすく、乾燥わかめやねぎは最初から入れると適度に戻りやすいです。
じゃがいもや大根など火の通りにくい根菜は、薄切りにして加熱時間を少し長めに設定すれば対応可能です。
また、ラップをふんわりかけて蒸気を逃がすことで吹きこぼれを防ぎ、仕上がりもきれいになります。
味噌を入れた後の加熱は短時間で十分なので、香りを逃さないよう注意しましょう。
電子レンジ調理は耐熱カップ一つで完結するため、忙しいときの即席ご飯や夜食、職場での簡易調理にも応用できます。
電気ケトルポット活用の即席一人分レシピ

ポットや電気ケトルを使えば、お湯を沸かすだけで即席味噌汁が可能です。
カップに具材と味噌、だしの素を入れ、熱湯200mlを注いでかき混ぜるだけ。わかめや乾燥ねぎなど「戻りやすい乾物具材」を常備しておくと便利です。
さらに工夫として、マグカップや保温性のあるタンブラーを使うと、時間が経っても熱々の状態で楽しめます。
油揚げや乾燥豆腐などを一緒に入れておけば、短時間で具だくさんの満足感が得られます。
また、オフィスや旅行先でも電気ケトルさえあれば調理可能なので、インスタント食品に頼らずに済み、栄養バランスも取りやすくなります。
具材をあらかじめ小分けしておく、味噌玉を持参しておくなどの工夫を組み合わせれば、より手軽で安定した味噌汁ライフを実現できます。
味噌玉の作り方~保存日数と冷凍解凍のコツ

味噌玉は「味噌にだしと具材を混ぜて丸めた保存食」です。
一人分の味噌15gに顆粒だし2g、乾燥具材を混ぜてラップで包み冷凍。保存は冷蔵で1週間、冷凍で1か月が目安です。お椀に入れて熱湯を注ぐだけで完成するので、忙しい人におすすめ。
さらに応用として、具材を変えることで味わいにバリエーションを出せます。
乾燥わかめ、ねぎ、油揚げ、乾燥豆腐などは解凍後も風味が損なわれにくく、味噌玉に向いています。
冷凍する際は一つずつラップに包んでからジップ付き袋に入れると霜がつきにくく、保存性が向上します。
解凍は基本的に熱湯を注ぐだけで良いですが、少し時間があるときは冷蔵庫に移して自然解凍すると風味が安定しやすくなります。
また、作り置きしておけばお弁当やアウトドアにも活用でき、忙しい毎日に強い味方となります。
具材の基本~豆腐・わかめ・ねぎの下ごしらえ

定番の具材は豆腐・わかめ・ねぎ。豆腐は1cm角に切り、わかめは水で戻し、ねぎは小口切りにして準備します。
下ごしらえの段階で余分な水分をきちんと切っておくと、仕上がりが水っぽくならず味が引き締まります。
また、豆腐は絹ごしにするとなめらかな口当たりに、木綿豆腐にすると食べ応えが出て満足感が増すなど、種類によって仕上がりの印象が変わります。
わかめは乾燥タイプなら戻し時間を短くしすぎないことが大切で、戻しすぎても食感が損なわれるので注意が必要です。
ねぎは青い部分を多めにすると香りが強く出て、白い部分を使うと甘みが感じられます。
こうした小さな工夫を加えるだけでも、毎日の味噌汁に変化をつけられるでしょう。
さらに、豆腐を温めすぎると崩れやすいため、鍋に入れるタイミングを最後にするのがおすすめです。
「豆腐+わかめ+ねぎ」の組み合わせは失敗しない黄金比であり、味と栄養のバランスが取れた一杯に仕上がります。
野菜具材おすすめ10選!キャベツ・大根・玉ねぎなど

一人分でも野菜をしっかり摂るなら、以下の具材がおすすめです。
それぞれの野菜には栄養や食感の特徴があり、組み合わせによって味噌汁の表情が豊かになります。
- キャベツ(ざく切り):柔らかく甘みが出やすい。ビタミンCも補給できる
- 大根(いちょう切り):さっぱりとして消化を助ける。火を通すと甘みが増す
- 玉ねぎ(薄切り):加熱すると自然な甘みが広がり、旨味がアップ
- にんじん(短冊切り):彩りが良く、βカロテンを豊富に含む
- ほうれん草(下ゆで後):鉄分や葉酸を補給でき、彩りも鮮やか
- かぼちゃ(薄切り):甘みが強く、食べ応えのある仕上がりに
- なす(半月切り):だしをよく吸い、柔らかな食感が特徴
- しいたけ(スライス):旨味成分グアニル酸で味を深める
- ごぼう(ささがき):香りと食感がアクセントになり、食物繊維も豊富
- 小松菜(ざく切り):カルシウムが多く、後から加えると鮮やかな緑色が残る
火の通りやすい切り方を意識すれば短時間で仕上がります。
さらに季節の野菜を少し取り入れると、栄養面のバランスが整うだけでなく、飽きずに続けやすい味噌汁になります。
例えば春なら新玉ねぎ、夏はオクラやトマト、秋はさつまいも、冬は白菜などを加えると、旬の味覚を楽しめます。
たんぱく質具材おすすめ5選!豆腐・油揚げ・卵・鮭・鶏むね

味噌汁はたんぱく質を補える一品としても優秀です。
特に一人暮らしでは肉や魚を十分に用意できない日も多く、味噌汁に少し工夫を加えるだけで不足しがちな栄養を効率よく摂取できます。
- 豆腐:絹はなめらかで上品な食感、木綿は崩れにくくしっかりした噛みごたえが魅力。カルシウムや植物性たんぱく質が豊富
- 油揚げ:湯通しして油抜きすると余分な油が落ち、だしを吸って旨味が増す。冷凍保存もしやすく常備に便利
- 卵:溶き卵を流し入れるとふんわり仕上がり、半熟状態で火を止めると優しい口当たりに。ビタミンやミネラルも摂取可能
- 鮭:焼き鮭を加えると贅沢感が増し、DHAやEPAなどの良質な脂質も一緒に摂れる。切り身を少量残して利用するのもおすすめ
- 鶏むね:薄切りにして火を通すと食べ応えがあり、脂肪分が少なくヘルシー。下味を少しつけてから入れると風味がアップ
これらの具材はどれも少量で栄養価を高めることができ、主菜を少なめにした日の栄養補強にも最適です。
また、豆腐+卵や鮭+ねぎなど、複数を組み合わせればボリューム感が出て一杯で十分満足できる味噌汁になります。
味噌の種類選び~赤・白・合わせの違いと相性

味噌には赤味噌・白味噌・合わせ味噌があり、地域や家庭によって伝統的に使い分けられています。
赤味噌は東海地方を中心に親しまれ、濃厚でコクが深く塩味が強めで、魚介類や肉など旨味の強い具材と相性が抜群です。
一方、白味噌は関西や西日本で多く使われ、発酵期間が短く甘みが特徴的で、豆腐や野菜、根菜類などと合わせると優しい味わいに仕上がります。
合わせ味噌は赤と白の良さを取り入れたもので、地域に関わらず広く使われ、バランスのとれた味が楽しめるため初心者にも最適です。
また、家庭によっては米味噌や麦味噌を取り入れることもあり、米味噌は全国的に最も一般的でクセが少なく万能に使えるのが特徴です。
麦味噌は九州地方を中心に親しまれ、香りが豊かで甘みが強く、特に野菜たっぷりの味噌汁に向いています。
さらに具材との相性を考えると、魚介系には赤味噌、淡泊な豆腐や青菜には白味噌、幅広く使いたいなら合わせ味噌と、組み合わせ次第で印象が大きく変わります。
毎日飲む場合は数種類を常備しておき、気分や献立に応じて使い分けると飽きずに楽しめます。
減塩のコツ~塩分目安とカロリーの考え方

味噌汁一杯の塩分は約1.5〜2g。減塩を意識するなら、だしを濃いめにとり、味噌の量を控えるのがポイントです。
また具材に野菜やきのこを多く加えると、自然な旨味で薄味でも満足感が出ます。減塩味噌を使うのも有効です。
さらに工夫として、具材にカリウムを多く含むほうれん草やじゃがいも、なすなどを取り入れると、体内のナトリウム排出を助けて減塩効果が高まります。
出汁を昆布やしいたけなど天然素材からとれば旨味が増し、塩分を控えても物足りなさを感じにくくなります。
カロリー面でも、油揚げや肉類を加えるより野菜や豆腐を中心にすると一杯あたりの総カロリーが抑えられ、栄養バランスの改善につながります。
こうした工夫を積み重ねることで、毎日安心して続けられる減塩味噌汁になります。
よくある失敗~薄い・濃い・分離・生臭いを防ぐ対策

味噌汁作りでよくある失敗は「味が薄い・濃い」「味噌が分離する」「だしが生臭い」といったものです。これを防ぐには:
- 薄い→味噌を追加する前にだしを減らす。塩分を足すのではなく、水と味噌のバランスを整える意識を持つとよい
- 濃い→お湯を足して調整。可能ならだし汁を加えて旨味を保つと味がぼやけにくい
- 分離→味噌を完全に溶き伸ばす。おたまに取り、少しずつだし汁で溶かすことで均一に混ざる
- 生臭い→だしを沸騰させすぎない。特に煮干しやかつお節は強火で長く煮ると臭みが出やすいため注意
また、具材の入れるタイミングが遅すぎたり早すぎたりしても味にムラが出やすいため、根菜類は早め、葉物は最後にと火の通りに合わせるのがポイントです。
加えて、味噌は保存状態によっても風味が変化するため、冷蔵保存を徹底し、古くなったものは使わないことも重要です。
こうしたちょっとした工夫を積み重ねるだけで、安定した美味しさが出せるようになります。
洗い物最小化!ミニ鍋や計量器具の選び方

一人暮らしでは洗い物が少ないことも重要です。
直径14cm程度のミニ鍋や、電子レンジ対応の耐熱カップを常備しておくと便利です。
特にミニ鍋は小回りが利くので、一杯分の味噌汁を作る際に余分な鍋を使わずに済み、後片付けも楽になります。
電子レンジ対応の耐熱カップは、そのまま食器代わりにもできるため、洗い物をさらに減らせます。
計量スプーンはスタッキングできるものを選ぶと収納も楽になり、省スペースでキッチンがすっきりします。
また、軽量カップ兼用のマグや目盛り付きカップを使えば、計量器具を一つ減らせるので効率的です。
さらに、シリコン製の小さな泡立てやマドラーを活用すると、味噌を溶かす作業も鍋やおたまを汚さずに済みます。
「使う器具を最小限にする」工夫を積み重ねることで、毎日の味噌汁作りが無理なく続けやすくなります。
ちなみに管理人以下のミルクパンを一人分味噌汁用に愛用しています。
作り置き保存容器~冷蔵・冷凍・温め直しの注意点

作り置きした味噌汁は冷蔵で2日、冷凍で1か月が目安。
ただし冷凍は具材が変質することもあるため、具材は冷凍保存せず「だし+味噌」で保存するのがおすすめ。温め直す際は必ず弱火で加熱し、沸騰させないことが風味を守るコツです。
さらに、保存容器を選ぶ際には密閉性が高いものを用意すると安心です。
特に冷蔵保存では匂い移りを防ぐためガラス容器やフタ付きタッパーを使うと良いでしょう。冷凍する場合は小分けにしておくと必要な分だけ解凍できて便利です。
また、再加熱の際は電子レンジを使う場合でも必ずラップをかけて加熱し、吹きこぼれや乾燥を防ぐのがポイントです。
再度具材を追加したいときは、火を止めてから入れると食感が損なわれにくくなります。
こうした工夫を加えることで、作り置き味噌汁の味を最後まで美味しく保つことができます。
味噌汁の作り方一人分~5分で完成の段取り

最後に、5分で味噌汁を完成させるための段取りを紹介します。
- 水200mlを鍋または耐熱カップに入れる
- だしの素を加えて加熱開始(火加減は中火、電子レンジなら600W2分程度)
- 加熱中に具材を切る(豆腐・ねぎ・乾燥わかめなど手早く準備)
- 加熱が終わったら具材を投入し、さっと火を通す
- 火を止め、味噌をおたまにとってだし汁で溶き伸ばし、全体に加える
- 弱火で数十秒温度を整え、器に盛り付けて完成
「並行作業」を意識することで、実際の調理時間は5分程度で済みます。
さらに慣れてくれば包丁を使わずにカット済み野菜や冷凍具材を利用し、ラップや耐熱マグを活用することで洗い物も最小化できます。
段取りを工夫すれば、朝の限られた時間でも栄養ある一杯を手軽に作れるようになります。
味噌汁の作り方一人分まとめチェックリスト

- 水の基本量は200ml(お椀のサイズに合わせて150〜220mlで微調整可能)
- 味噌は大さじ1弱(約15g)を目安に、種類によって増減させる
- だしの素は小さじ1/2。白だしなら大さじ1が基準
- 味噌は必ず火を止めてから溶かす。おたまでだし汁を加えて丁寧に伸ばすと均一に仕上がる
- 電子レンジや電気ポットでも代用可能で、忙しい朝や夜食にも対応できる
- 具材は豆腐・わかめ・ねぎが鉄板。野菜や卵、鮭などを組み合わせれば栄養バランスも良くなる
- 保存は冷蔵2日・冷凍1か月が目安。作り置きする場合は「だし+味噌」の状態で保存すると風味が落ちにくい
- 減塩を意識するならだしを濃いめにとり、味噌をやや控えめに。具材に野菜やきのこを加えると自然な旨味で満足感が出る
毎日の一杯をシンプルに、おいしく、そして栄養を意識しながら無理なく続けられる工夫が大切です。












